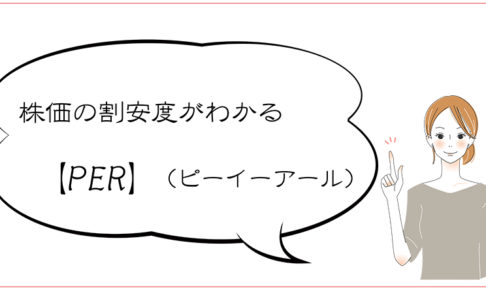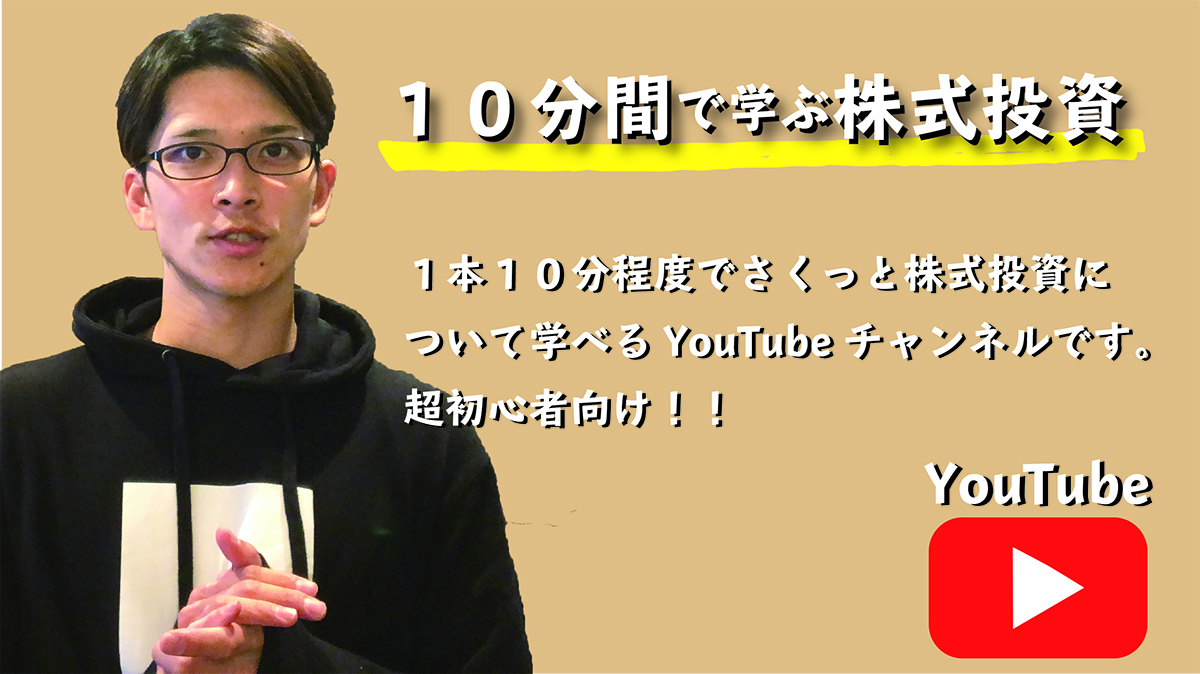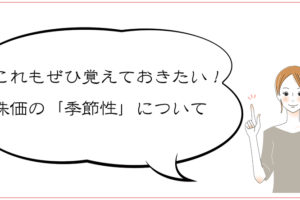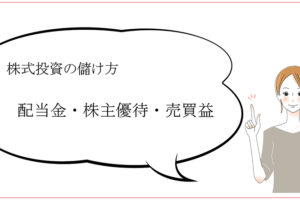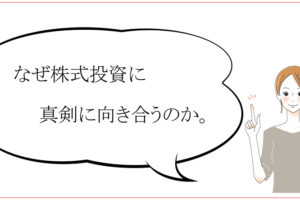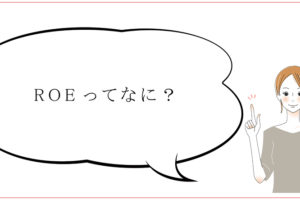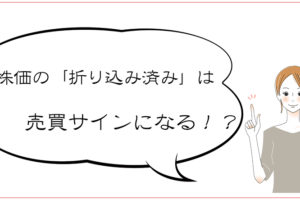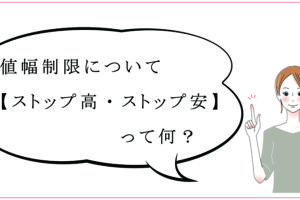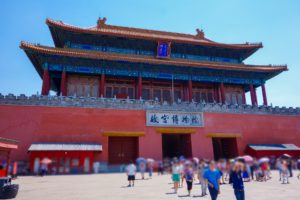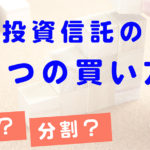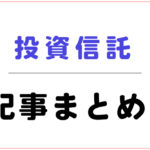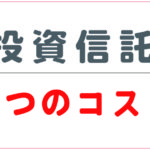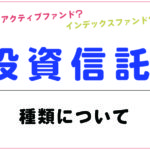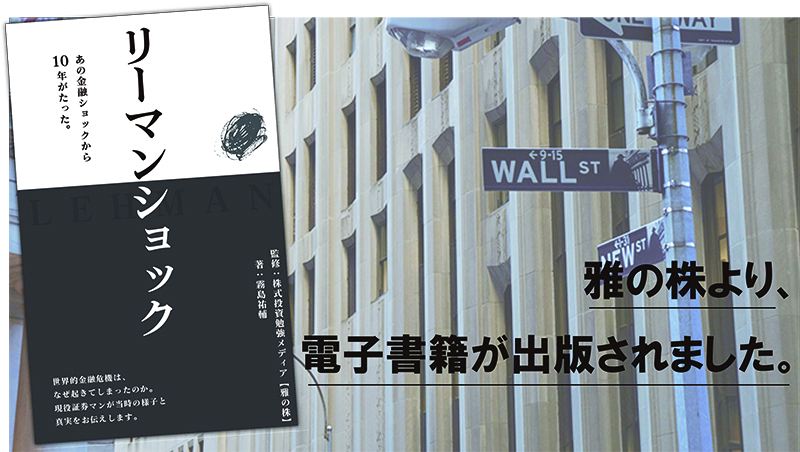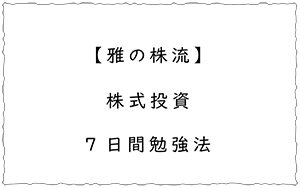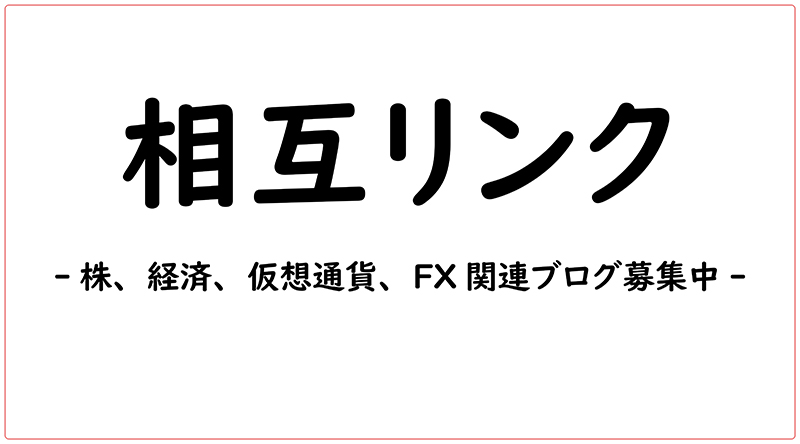こんにちは、雅の株~「超初心者」から「初心者」になるためのブログ~にアクセス頂きましてありがとうございます。
本日は、『バブル』という言葉について書いてみたいと思います。
皆さんも言葉は聞いたことがあると思いますが、経済史上において有名なバブルは1980年代の『バブル経済』と、2000年前後の『ITバブル』がありますね。
バブルが一体どういうものか、簡単に振り返ってみましょう。
バブルとは

1980年代の『バブル経済』と2000年前後のITバブル
バブルというのは、簡単に言うと『株』や『不動産』などの価格が、実態の価値とは大きく離れ高騰してしまう現象のことを言います。
有名なバブルは1980年代の『バブル経済』と、2000年前後の『ITバブル』があります。
『実態の価値とは大きくかけ離れ』というのがポイントなのですが、例えば企業で言うと、売上が伸びていないのにどんどん株だけが買われて株価が上昇してしまっている、そんなイメージです。
余談ですが、実はこのブログの読者さんは25~35歳くらいの年齢層の方によく読まれている傾向がありますので、バブル経済の頃に生まれた方がたくさんいらっしゃるということです。
バブル景気
日経平均株価は3万8915円87銭まで上昇
バブル景気とは1986年から1991年までの4年間の間続いたとされています。
日経平均株価は約4万円近くまで上昇しました。
2018年6月現在の日経平均株価は22700円前後ですので、その高さがよくわかりますね。
土地や不動産価格も急騰しました。
全米の面積は東京23区の面積の15000倍もあるのにも関わらず、東京23区の時価の合計と全米の時価の合計が同じになる程にまで膨れ上がったのです。
この頃のPERは約50倍、地価はそれまでの約2倍まで膨れ上がったため、どれだけ割高水準だったかがわかります。
ITバブル

ITバブルはインターネット関連企業に対する期待値が度を過ぎて高まり、それら関連企業の株が異常なまでに買われたことを言います。
上の図はITバブル期のソフトバンクの週足チャートです。
その象徴ともいえるソフトバンク株は、2000年前後までに120倍に上昇し、その後は80分の1になるまで急降下していきました。
情報・通信のインフラがインターネットに置き換わりはじめた中で、インターネット関連事業の将来性に対する異常なまでの『期待感』が引き金となったわけです。
なぜバブルが起きるのか!?
過度な期待感
それではなぜバブルというのが発生するのでしょうか。
例えば1980年代のバブル景気には、【アメリカの貿易赤字>プラザ合意>円高不況>低金利政策>バブル】という流れがあるのですが、細かい背景は当記事では割愛します。
バブル景気にもITバブルにも共通して言えることは、期待感が異常に膨らんだことが原因で起きたということ。
『今株や不動産を買っておけば、今後上がり続けるから儲かる!』『インターネット関連株は間違いない!』という過度の期待値によって買われすぎることから、どんどん実態価値と乖離していくわけですね。
実態価値から大きくかけ離れて膨れ上がったバブルというのは、いずれ破裂してしまいます。
これが『バブルの崩壊』ということになり、株価は一気に急降下します。
そして売りが売りを呼ぶことで雪だるま式に株価は下落し、株価低迷期に突入するわけですね。
資産を根こそぎ失った人もたくさんいたと聞きます。
PERを考える
PER
それでは現在の株価がバブルかバブルではないかを考えるにはどうしたらいいのでしょうか?
それは、単純ですが『PER』を常に意識することです。
このブログでも何度も取り上げている通り、PERは株が買われすぎていないかを判断することのできる一つの指標です。
2018年現在の平均PER水準は、約14倍前後です。
それではバブル期のPERはどうでしょうか。
1990年当時の日経平均PERは約80倍で、ITバブルの時のインターネット関連銘柄のPERは軒並み100倍以上という数字をたたき出していました。
現在のPERの水準からみると、いかに割高だったかが分かります。
まとめ
バブル期がいかに実態とかけ離れて株が買われていたかがお分かり頂けたと思います。
ただし、逆を返せば、現在の日経平均のPERの水準を見てみると、世界的にも平均的な推移を維持していると言えます。
つまり株価に対してある程度企業や経済の実態価値が伴っているということです。(筆者の個人的な意見ですが。)
これからも株価というのは絶えず動き続けていきます。
このブログを読んでくださっている投資初心者の方は、企業の株価だけではなく、PERなどを常に意識してみると良いと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。