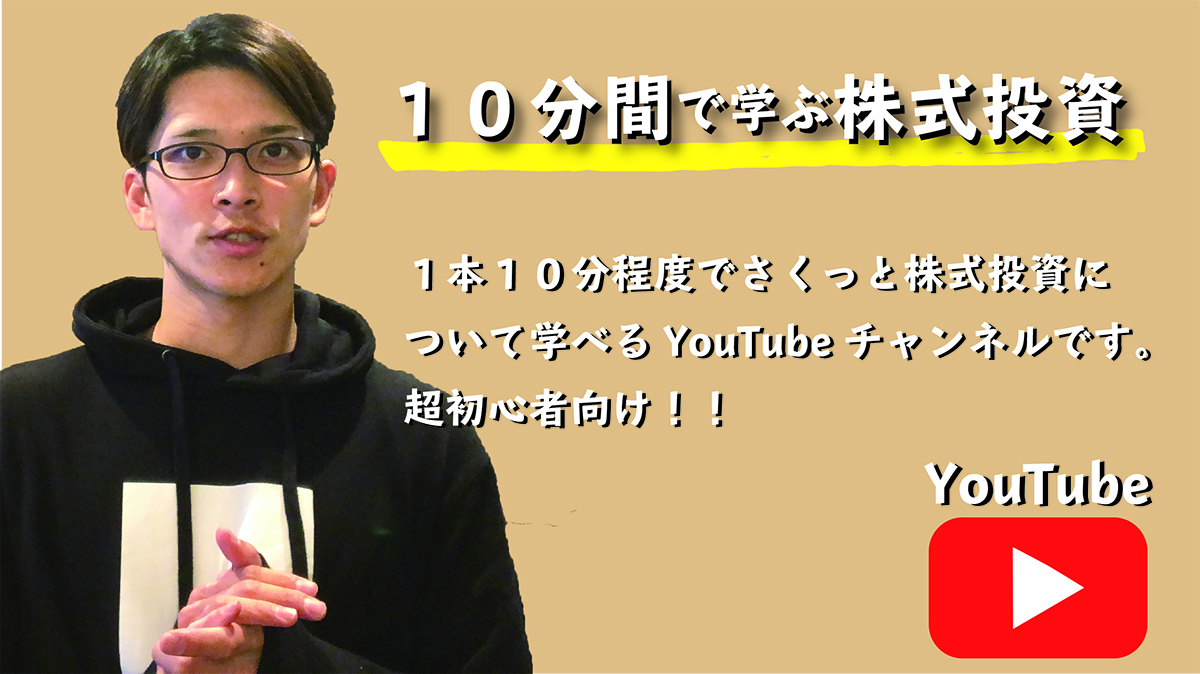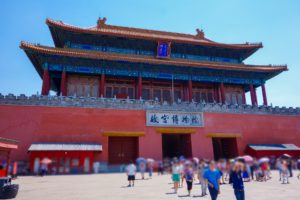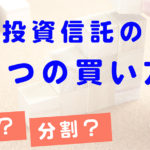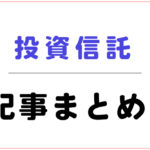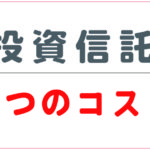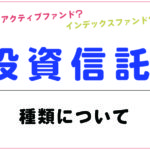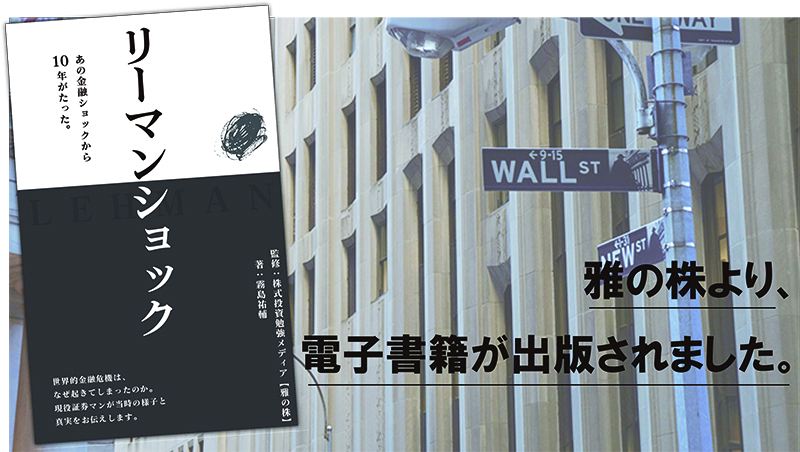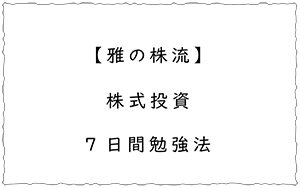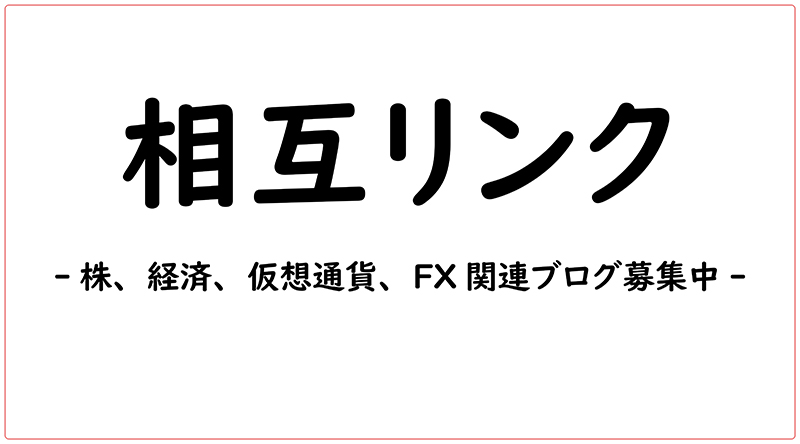現役証券マンの経済コラム
~お金の流れで世界を知る~
こんにちは、雅の株ブログで経済コラムを担当している霧島です。
さて、この度金融庁から年金に関わる指針が発表され、その中で「老後資金として2000万円を用意する自助努力を促す文章」が話題となっていますので、今回はその件について考えていきたいと思います。
日本の年金制度
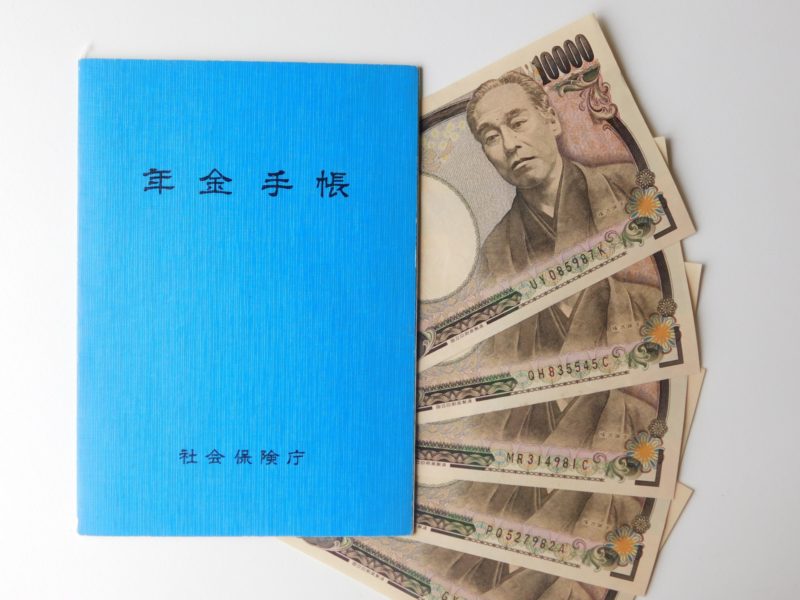
先に確認しておきたいのは「日本の年金制度は破綻しない」という点についてですが、年金機構自体が破綻するということは無いと思いますが、「制度としては既に破綻している点」について確認しておきます。
制度自体が破綻しているという考えは「高齢化社会」の観点から、学校の授業でも出るほど有名であるので割愛します。
人口が減っていく中で、若い世代が現在の高齢者を支えていくのは非常に難しくなってきているのは明らかですし、生産年齢が高齢者の年金を賄う制度自体が、すでに現状の日本において通用しなくなっている時点で制度としては終わっていたのです。
GPIFの現状

年金の運用母体はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)という機関が担当しており、ここが国民の年金の一部を運用して、高齢者の生活にお金を回しています。
GPIF自体は年間6%と言う運用目標をもって運用していますが、つい数年前までは運用資金がほとんど国債などで運用していたため、運用利回りはとても低い環境でした。
しかしながら、この国債運用の手法を、株式や外国証券などを含めて年間6%の運用を目指さなくてはいけなくなったのは、当時の運用資産約125兆円のうち「毎年の取り崩し金額が8兆円に迫る金額になっていた」からです。(GPIFの運用取り崩し金は、年金給付の一部です。)
資金が全く増えない状態で、年間8兆円を取り崩していくと、約15年後にはGPIFの運用資産が底を付きます。
このような理由から、GPIFは現状「運用をしたくてやっているわけではなく、運用の必要性に迫られてやっている」という側面が見えてきますね。
老後資金『2000万円』の内訳
「老後資金として2,000万円」が足りないというニュースが飛び交っており、政府は金融庁のこの報告を認めないと言い出す始末であります。
先に言っておきますが、金融庁の報告は、ずば抜けて頭の良い人たちが2時間の会議を12回も重ねて出した試算なので、かなり精度の高い数字だと思います。
この数字を「選挙に影響する可能性が高いから撤回させる」という考えを持ち出す政府の方がどうかしています。
話を戻して、2000万円についてですが、勘違いしてはならないのは「2,000万円なくても老後生活は可能です」という点です。
これは金融庁の試算にも書いてある話ですが、この年金では足りない2,000万円は「ゆとりある老後生活」を送るために必要な資金であると考えてください。
無職世帯の月の平均支出は26万円程度(様々なデータがあるので必ずではないです。)と言われており、夫65歳・妻60歳の平均的な年金収入が21万円程度と言われています。
この場合に年金支給額から月の平均支出を引くと、5万円程度足りなくなる計算です。
これが65歳の退職後から、95歳になるまで続くと、
5万円×12カ月×30年=1,800万円
となるため、少し多めに計算した
6万円×12カ月×30年=2,160万円
との間を取って2,000万円程度足りなくなると試算していると考えます。
娯楽と交際費
では、なぜ2,000万円がないとゆとりある老後生活が送れないかというと、この足りない5万円、実は金融庁の報告における『ある出費』を無くせば必要のないお金だからです。
その減らさなくてはいけない出費は「娯楽と交際費」です。
ある保険会社が試算している約25万円の老後支出の内訳では、
教養娯楽費:27,000円
交際費:29,000円
合計:56,000円
の月の支出計算となっています。
これは「老後に楽しみたいこと」として上位にランクインしている旅行やグルメを試算に入れた結果です。
つまり、金融庁としては「年金で生活ができなくなるので2,000万円貯めてね」というわけではなく、
「年金のお金以外で色々と楽しみたかったら、2,000万円程度用意しといてね」
ということなのです。
まとめ
このような試算を行って事実を述べた金融庁、金融機関関係者からしてみたら「報告書の自助努力なんて昔から金融庁は言ってたじゃん」って感じです。
これを取って「2,000万円無ければ路頭に迷えということか?」とか「2,000万円足りないなんて話が違う」と言っているコメンテーターやワイドショーのコメントしている人は知識の無さを露呈しているだけですし、政府も今回の試算を撤回することは「国民に真実から目を逸らせる」ことになります。
この試算を行ったメンバーは今回の報告書に名前が載っています。
名立たる金融機関の役職員や大学教授など、多岐にわたる有識者の方の努力を無に帰すことの無いように、真実から目を逸らさずに虎視眈々と運用をしていきましょう。