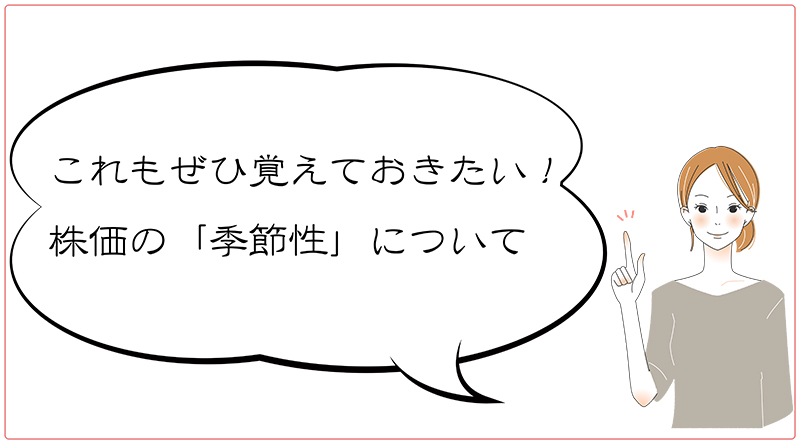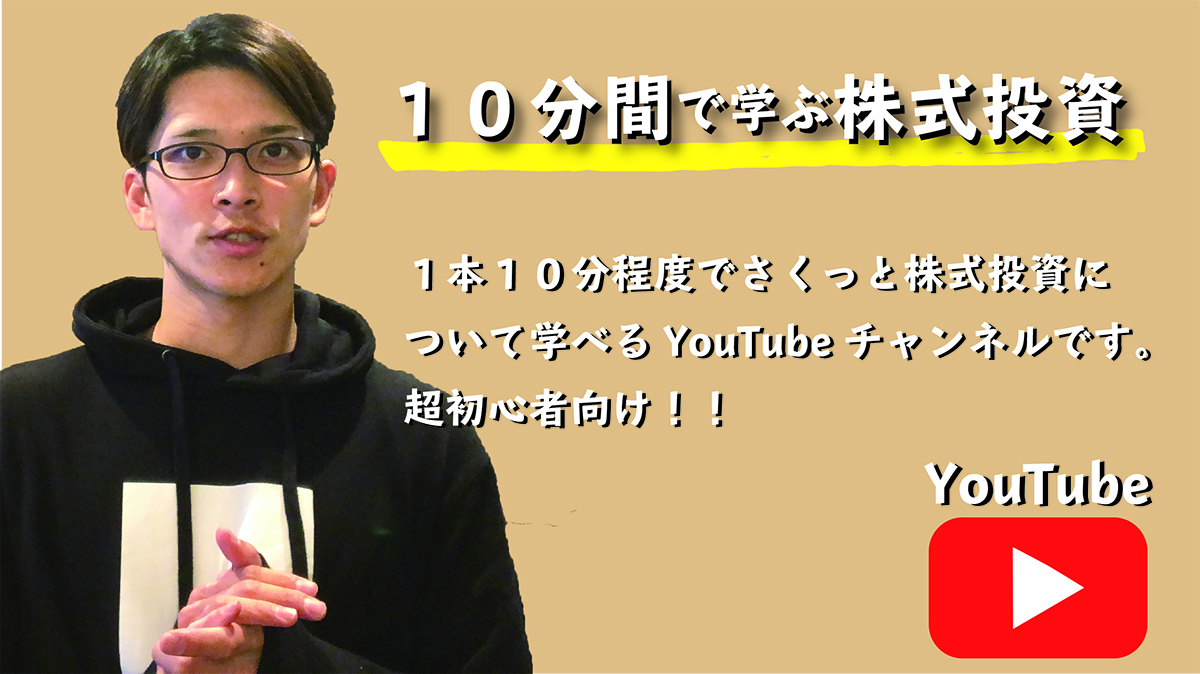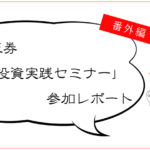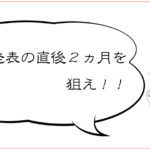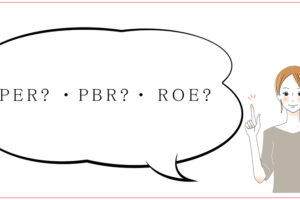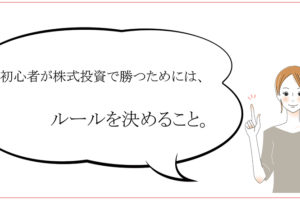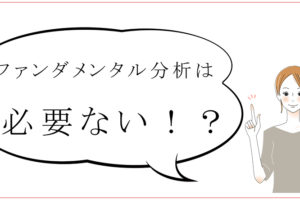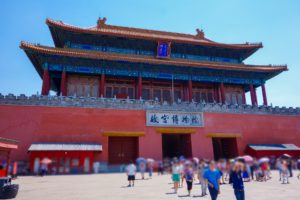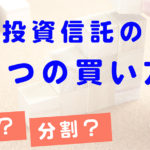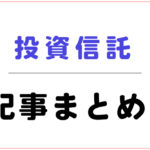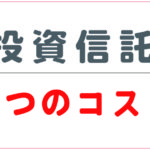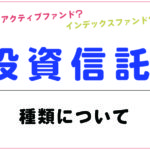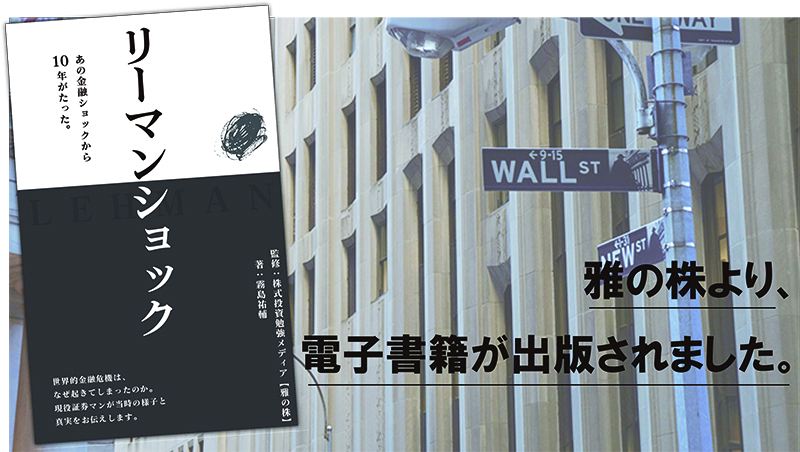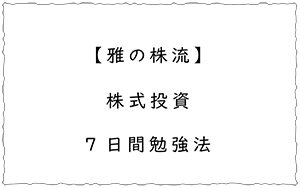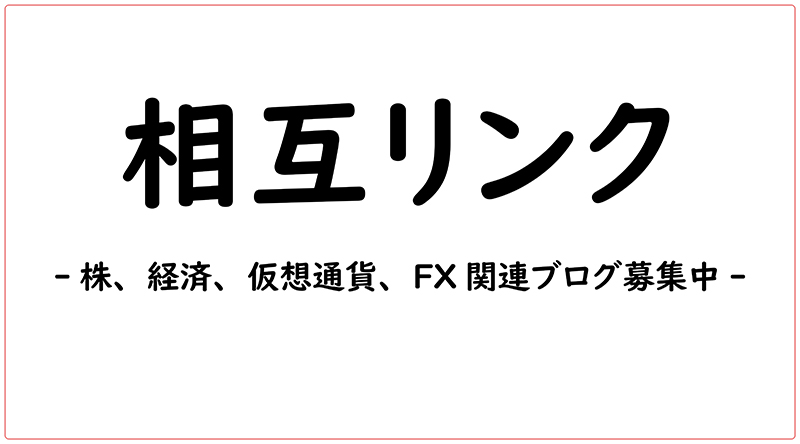こんにちは、雅の株~「超初心者」から「初心者」になるためのブログ~にアクセス頂きましてありがとうございます。
実は株価にも「季節性」というものがあるのをご存知でしょうか。
あくまで統計学をもとにしたデータですが、とても参考になるので是非、覚えておくといいと思います。
株価の歴史的な暴落は、10月に集中している

株価の動きにはよく知られている季節性があります。
秋に下落しやすく、春にかけて上昇しやすいというものです。
実際に株価は春頃に高値を付けて、夏には夏枯れ相場と言われる元気のない相場になり、秋に下がるケースがよく見られます。
こうした株式市場の習性をふまえて、アメリカでは「Sell in may and go away」という格言があります。
「5月に株を売って、その後はしばらく株などせずにどこか行ってしまえ」という意味です。
日経平均の月別の暴落状況を見てみると、
6~10月は下落しやすい
12~4月は上昇しやすい
という傾向が見られるのです。
もちろん、毎年必ずこうなるという法則ではありませんが、比較的高い確率でこういった株価の値動きが繰り返されています。
このような株価の季節性は、日本だけではなく、欧米なども含めて過去何十年にもわたって観察されているのです。
どうして秋に下落しやすいのか
どうして株価が秋に下がりやすいのかというと、世界的に12月が年度末である国が多く、年度末に向けて投資資金が新たな買いに動きづらい一方で、税金対策の処分売りなどが出やすくなる、という需給上の事情が大きいようです。
特に10月は世界的にも「魔の10月」と呼ばれるくらい株価が下落しやすい月であることが知られています。
1929年のブラックサーズデーや、1987年のブラックマンデー、さらに、比較的最近ではリーマンショック後の安値など、歴史的な大暴落は10月に集中しています。
春は投資成果が出やすく収穫の時期になりやすい
一方、12月から4月にかけては株価が上昇しやすい傾向があります。
12月はまだ年度末ですが、年度末に向けた売りが11月くらいまでにピークを迎えることが多く、12月は新年度入りへの期待感も高まって株価が上昇しやすくなるようです。
そして、1月はいよいよ世界的に新年度で新しい投資資金が株を買いに動き始めます。
世界的に「1月効果」と言われるくらい、1月は株価が上がりやすい傾向にある月です。
日本の場合は一般的に4月から新年度入りであり、3~4月の株価パフォーマンスが高くなる傾向があります。
もちろん、こういった「株価の季節性」は絶対ではありません。
この記事を書いているのが2017年10月25日ですが、24日の東京株式市場で日経平均株価は16日間続伸し、前日比108円52銭(0,50%)高い2万1805円17銭で終えました。
前日に記録した過去最長の連続上昇記録をさらに更新したことになり、終値は1996年7月11日以来およそ21年3ヵ月ぶりの高値圏になりました。
しかし、統計的に見ても「秋に買って春に売る」とということが、戦略的に有効であるということもまぎれもなく事実なのです。
スイングや長期投資をする際には、判断材料の一つにしてみてください。
お読み頂きありがとうございました。